2025.05.19(Mon) お知らせ
部下の メンタル 不調に気づく管理職の観察と声かけのコツ|精神保健福祉士が解説
部下の メンタル 不調に気づく管理職の観察と声かけのコツ|精神保健福祉士が解説
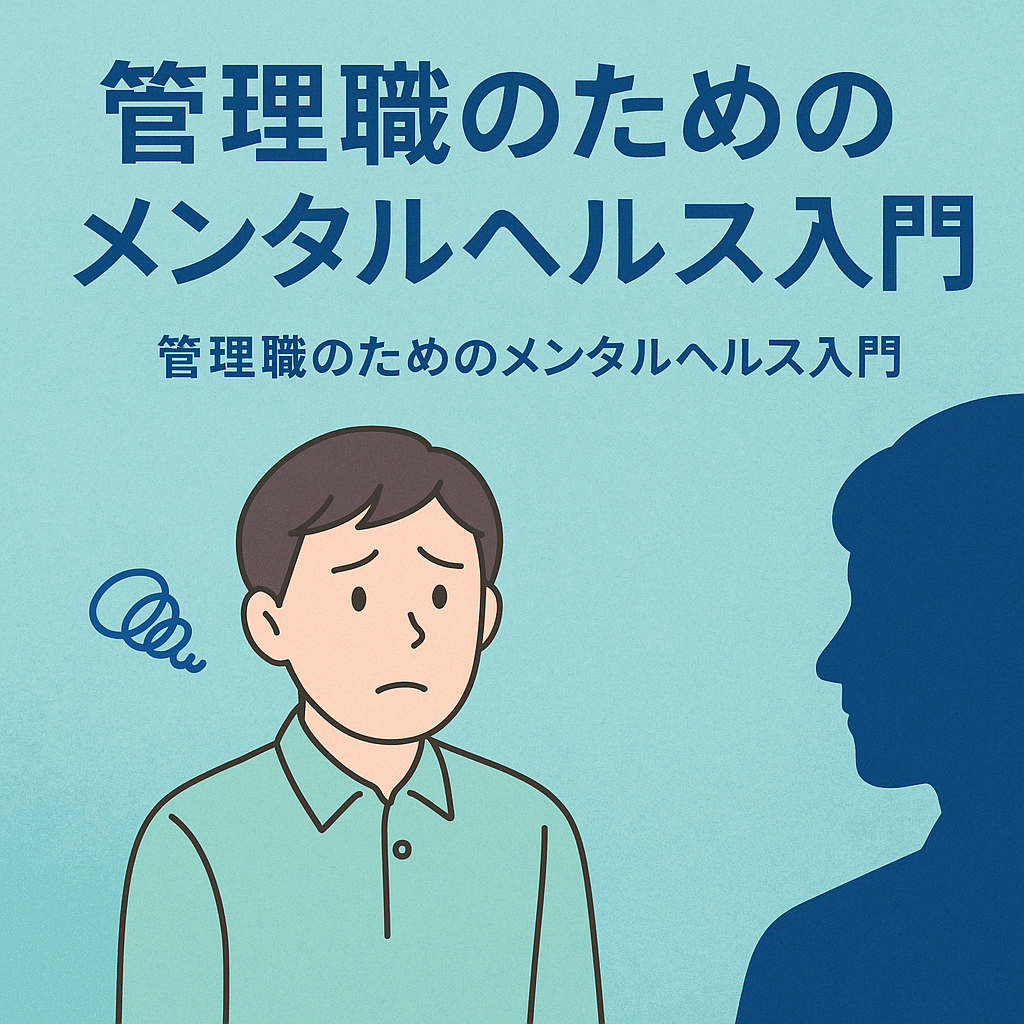 「最近、部下の元気がない気がするけど、忙しくて様子を見る余裕がない…」そんな不安を感じたことはありませんか? 部下の メンタル ヘルス不調は、重大な問題に発展する前に“気づくこと”がとても大切です。特に、日々部下と接する機会が多い管理職には、早期発見の「観察力」と「声かけの力」が求められます。 本記事では、精神保健福祉士の視点から、管理職が職場で実践できる3つの基本ポイントをご紹介します。
「最近、部下の元気がない気がするけど、忙しくて様子を見る余裕がない…」そんな不安を感じたことはありませんか? 部下の メンタル ヘルス不調は、重大な問題に発展する前に“気づくこと”がとても大切です。特に、日々部下と接する機会が多い管理職には、早期発見の「観察力」と「声かけの力」が求められます。 本記事では、精神保健福祉士の視点から、管理職が職場で実践できる3つの基本ポイントをご紹介します。
1. 表情・口数・服装など「日常の変化」に敏感になる
不調のサインは、業務成績や明確なミスとして現れる前に、日常のふとした変化として現れます。たとえば:
- 笑顔が減った・目を合わせなくなった
- 挨拶や会話が減った
- 服装や髪型が乱れている
こうした変化に気づくには、「普段の状態を知っていること」が前提です。日ごろから自然なコミュニケーションを心がけ、変化に気づける関係性を築いておきましょう。
2. 「ちょっとした声かけ」で“気にかけている”ことを伝える
どう声をかけていいか分からないという声をよく聞きます。ポイントは、深刻な話をするのではなく“気にかけているよ”というメッセージを日常の中に織り交ぜることです。 例:
- 「最近ちょっと疲れてるように見えるけど、大丈夫?」
- 「前より元気がないように思うんだけど、何かあった?」
“あなたを気にかけている”という安心感を伝える一言が、相手の本音を引き出すきっかけになります。
3. 管理職自身が「背中を見せすぎない」ことも大切
管理職自身が「常に完璧」な姿を見せすぎると、部下は「相談しにくい」と感じてしまいます。 ときには、
- 「最近ちょっと疲れててさ」
- 「無理しすぎてない?」
と、弱さやゆるさを言葉にすることで、部下も安心して話しやすくなります。心理的安全性のある職場づくりに繋がります。
まとめ
メンタル ヘルスは「気づき」が何より重要。管理職の小さな気づきと声かけが、職場の安心感をつくります。特別な知識がなくても、今日から実践できることばかりです。まずはひとつ、始めてみませんか?
\職場の メンタル ヘルスに関する研修をご希望の方へ/ 当社では、精神保健福祉士による「管理職向けメンタルヘルス研修」を実施しています。 詳細はこちらからお気軽にお問い合わせください。 #メンタルヘルス #職場のメンタルヘルス #メンタルヘルス研修 #メンタル不調に気付く #管理職の悩み #管理職研修 #職場のコミュニケーション #チームマネジメント #精神保健福祉士 #メンタルヘルス講師 #職場改善のヒント #心理的安全性 #人材育成 #職場改善

